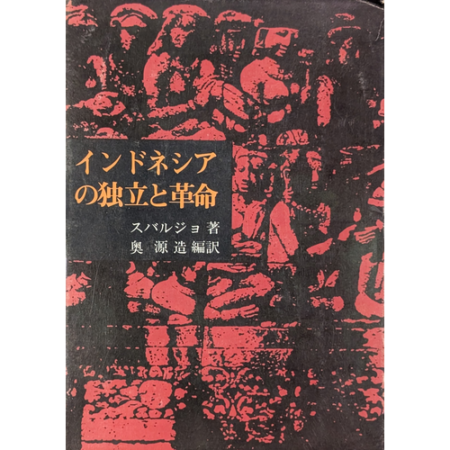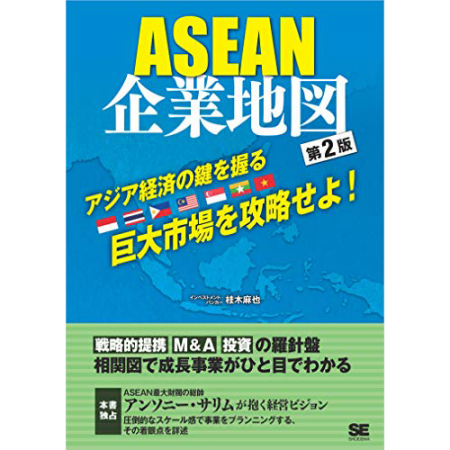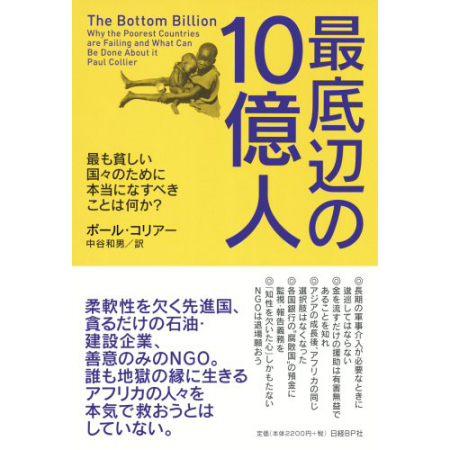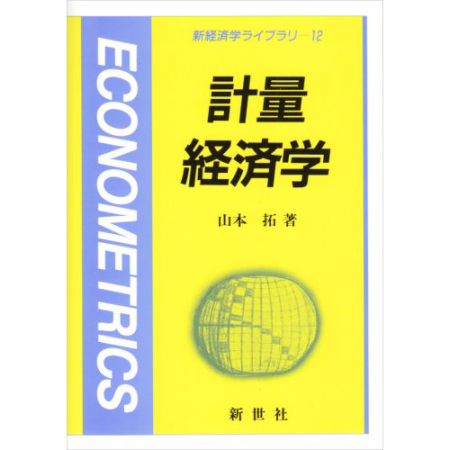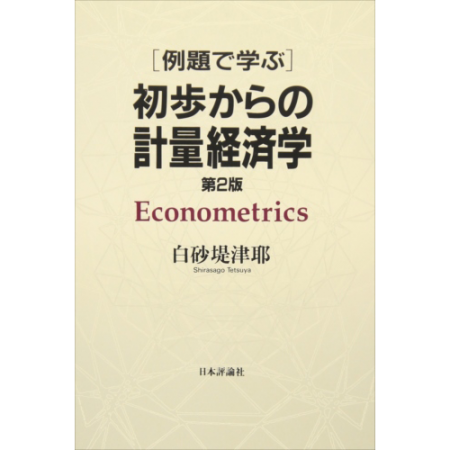日本の占領期に関するインドネシア史を知ろうとするとき、その書物や教科書や資料がスカルノ政権で書かれたものか、スハルト政権で書かれたものかを確認する必要がある。独立前後の要人は排除され、今の世代の歴史観は後者時代に作られたもの。当時の史実は中の人だった当人の書物を当たるのが良い。
この本は、インドネシア独立に際し、スカルノとハッタの陰でプロデューサーの役割を果たしたスバルジョの自伝。独立宣言の作成や、独立宣言前夜の緊迫した状況に携わった当事者による歴史の記録である。
インドネシア独立前夜にスカルノとハッタと行動を共にしていたスバルジョ。歴史はまさに偶然の連続。有名な二人だけでなく、スバルジョ、日本海軍人、日本陸軍人、そのほかの多くの役者がいて、一人でもかけたり、一人でも違う行動をしていたら今のインドネシアはなかった。独立前夜の時間単位の行動記録が圧巻。1973年の書籍であるため、入手が難しいが、ぜひ手に撮って欲しい一冊。
以下は、直接の引用ではなく、興味深かった部分の抜粋と要約であり、一部所感を付している。
「日本が1905年に日ロ戦争で勝利を収めて以来、アジア全域で民族主義精神が広まった。日本とタイを除くアジア全域が西欧の政治的・経済的な支配下にあった。1905年はアジア史の転換期であった。」
「フィリピン人とインドネシア人は人種的に近いものの、フィリピン人が個人主義に基づく国家と社会を形成したのに対し、インドネシア人は祖先の文化的な伝統に従って生活を守り続けた。」
これは統治手法の違いからくるものであり、フィリピン人がスペイン(住民を征服して統治することを目的としたため、宗教や文化を変えようとした)とアメリカ(独立宣言に忠実に自由の価値観を持ち込んだ)に直接統治された一方、インドネシア人は首長等を介してオランダ(イギリスと同様に経済的に搾取することを目的としたが、社会変容は試みなかった)に間接統治された。ジャワ人社会はヒンドゥー的な概念に大きく影響されており、カースト制が根強く残っていた。社会的な序列は、僧侶・哲学者・詩人・文人が最も高く、武士階級、商人・農民が続いた。
「日本統治下の独立準備委員会で憲法を起草するにあたって、インドネシア人の基本的な理念に基づく基礎的な事項として一般的に合意があった。
一、統一国家の理論を採択する。
二、連邦制に基づく国家構造を拒否する。それは連邦制が数千の島々からなる島嶼国に必要だという一体性の理念に矛盾するからである。
三、アメリカやフランスの革命の基礎をなしている個人主義的諸理論を拒否する。
四、反民主的とみなされる封建主義を拒否する。
五、国家元首は選出されるべきもので、世襲的なものではない。それ故、君主制を拒否する。
六、自由主義は、あらゆる社会的な局面で資本主義を鼓舞するが故に、拒否する。
七、マルクス階級闘争理論は、全国民の利益に反するが故に、拒否する。
八、独裁制と官僚性を拒否する。独裁制は、“ムシャワラ”や“ムファカット”あるいは公開の討論による合意達成という民主的な制度に反するからであり、官僚性は行政問題の円滑な解決を阻み、進歩への妨げとなるからである。
インドネシアの生活様式にみられる積極的な諸側面は、パンチャシラ(建国五原則)として、次のように定式化された。」
スカルノ政権時代にはこれらの原則は維持されていたが、スハルト政権時代にいくつかの点については方向転換がはかられたことが明確だ。外資へ門戸を開いたことで、より資本主義的な社会構造へ転換された。国家元首の世襲制は表向きは否定され続けているが、政治・経済活動のあらゆる面で親族を単位とする世襲が踏襲されている(相続税、贈与税が存在しないことも含め、政策にも反映されている)。また、身内を超えて調整・反論・議論による合意形成が行われにくい社会となっており、個人主義的な社会構造になっている。
「独立塾の組織化を委任されていたスバルジョは、インドネシア青年に高度な教育を与えるためのカリキュラム編成をすべて任されていた。オランダ人歴史学者ケーヒンは前田や陸海軍将校が共産主義的な陰謀に乗り出していたと論じたが、共産主義を科目として取り上げたことはなく、日本占領最終日まで一貫して共産主義思想は危険視されていた。」
スバルジョも、「日本は解放者ではなく、西欧の植民地主義者と幾分も違わなかった」と考えていて、「インドネシア社会に悲惨な惨禍をもたらした」としている。しかし、日本とインドネシアの両方が、お互いの利益のために互いを利用したことも事実である。日本がインドネシア民族運動を認めたのは、戦争目的の遂行を狙ったものであり、インドネシアの民族主義者もこれを利用して独立の達成を目論んだのだった。
「日本人は経済的にはインドネシア人に戦争経済のメカニズムを理解するように要請した。戦争経済は民族独立のために住民に大きな犠牲を要求するものであった。」
ジャワ島における反日運動の要因は、戦時経済による困窮と日本軍の苛烈な行為であった。オランダ植民地時代に長期間独立を果たすことはできなかったものの、食べる苦労、労務の苦労、独立を達成するために戦う苦労をインドネシア人は体験してこなかった。それゆえ、日本人が求めた「民族独立のために戦時経済を受け入れること」をインドネシア人はできなかったため、反日運動に繋がったと考えられる。
「民族運動は、オランダの支配下で、1930年から太平洋戦争の勃発する1942年まで、打つ手がなくなってしまっていた。民衆を封じ込めたオランダの政治機構は、日本軍のインドネシア侵略とともに破壊されたため、民族運動が復活した。」
「獄中にあった前田精少将が、1947年4月16日付けでオランダ領東インド検事総長へ提出した陳述書に、インドネシア独立前夜の動きが詳細に記録されている。8月15日午後3時、スカルノ、ハッタ、スバルジョが前田事務所を訪ね、日本の降伏の事実確認をしにきた。前田は香典を入手してから返答する旨伝えた。しかし、スカルノとハッタは同日夜に青年たちによって拉致され、6000人の義勇軍が深夜0時に放送局や通信機関や交通機関を占領し、全世界に独立宣言をするクーデターをはじめる企てをしていた。クーデターが起こると、権限を連合国へまだ委譲していない日本陸軍と全土のインドネシア人が交戦状態となるため、防がなければならなかった。スカルノとハッタは青年たちにクーデターを実行しないように説得したが、青年たちはこれに応じず。クーデターを8月17日の昼まで延期することだけを承諾した。スカルノとハッタは8月16日午後11時に前田邸を訪れ、独立宣言の準備をするための場所として使わせてほしいと依頼した。会合場所を見つけるための時間的余裕がなかったのだ。」
「8月15日夜、スカルノとハッタが姿を消した時の様子も克明に描かれている。郷土防衛義勇軍が大衆デモを計画していたことや、日本陸軍が人質として捕らえる懸念があったことから、青年たちがスカルノとハッタを守るために拉致監禁した。青年グループには、前田の指示でスバルジョが運営していた独立塾の部下ウィカナが関与していた。スバルジョはウィカナを説得し、最終的にはスカルノとハッタの居場所を突き止め、自らの車で迎えに行く。血気盛んな青年グループと郷土防衛義勇軍は、「たとえ日本軍によって数日内に叩き潰されたとしても、すぐに独立宣言を自分たちの手で世界に発信すべきだ」と主張していた。スバルジョ、スカルノ、ハッタは国際法に倣い、日本軍は連合軍の到着までに治安維持を担うことから、外交交渉なしの独立宣言は意味がないと主張した。最終的にスバルジョは、独立義勇軍へ「翌日正午までに独立を宣言できなければ、私を射殺してよい」と啖呵を切り、スハルトとハッタをジャカルタへ連れ返すことに成功した。」
8月16日夜から17日6時にかけて行われた独立準備委員会メンバーによる独立宣言文の作成に関する様子が克明に記録されている。独立準備委員会の老獪なメンバーは外交をよく理解していて、国際法上も日本軍は治安維持義務を負っていることをよく理解していた。日本と極端に対立しない形で、日本と無関係にインドネシア人が独立を宣言することで、日本海軍と調整するなど、したたかな姿勢で臨んでいた。一方、血気盛んな青年グループはスカルニを筆頭に、宣言文に日本を挑発し、対立を煽る文言を入れることでインドネシア人のプライドを示すことに固執したり、署名者の選定に関する議論では自分たちの手柄を示すために名前を入れることに固執したりしていた。たとえそれが暴力革命を引き起こし、日本軍の鎮圧によって束の間の独立となってもよいとすら捉えていたようだ。老獪なスバルジョ、ハッタ、スカルノらに説得される形で、インドネシアは日本と対立することなく、ギリギリのところで独立宣言を行った様子が描かれている。歴史とはまさに綱渡りであり、偶然の連続なのだとわかる。