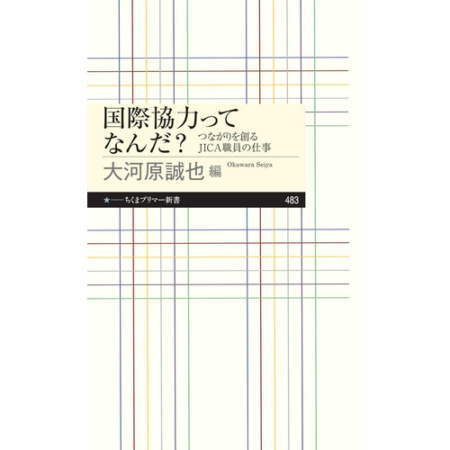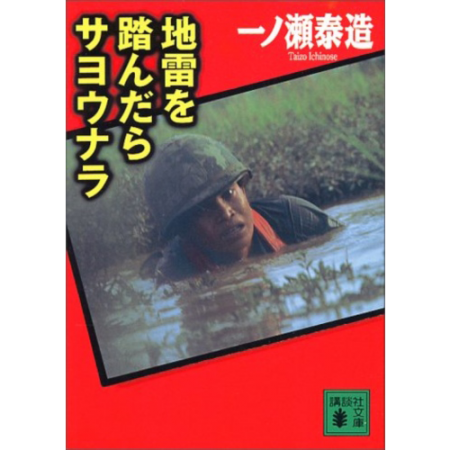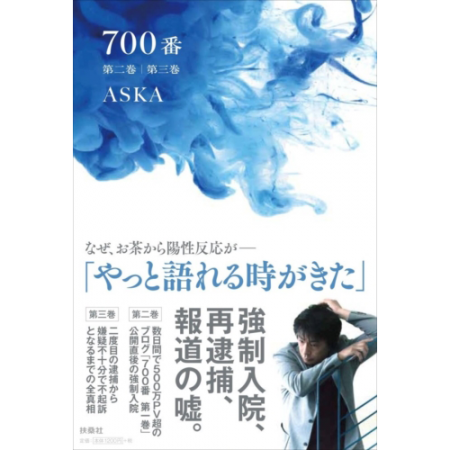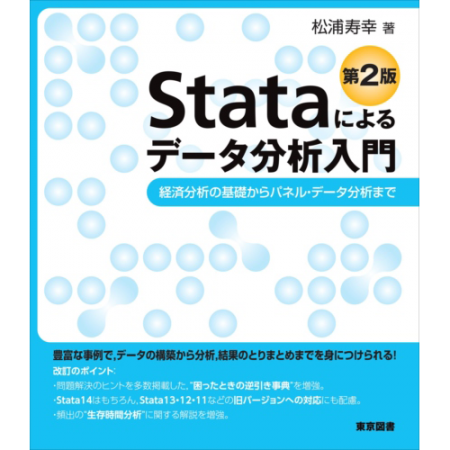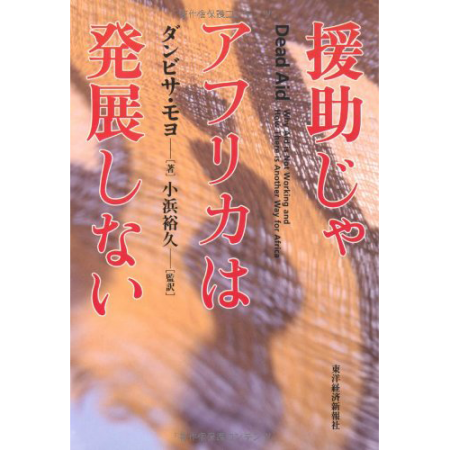国際協力ってなんだ?つながりを創るJICA職員の仕事
¥990
JICA若手職員が書いた本をJICA本垢が広報するというのは、時代の大きな前進を感じる。国の組織内にいたことがある人にはこの感動が伝わるだろう。
現役JICA職員の日常が書かれた本で、JICAが何をしているのか知らずに議論している人は、まず読んでみること。専門用語も多いが、丁寧に解説されている。ODAの上流下流、前線後方がよくわかります。1997年生まれの方もいて、思わず自分の生年月日と引き算してしまうことも。
伊藤さんのバングラデシュの堤防建設事業の話がおもしろい。雨季に毎年決壊する堤防を日本の技術で壊れないものを導入した話。雨季に増水した水面を船で往来する住民が堤防を壊して航路を作り、洪水が起きる悪循環を、対話や仕組みを作ることで解決した話。
管理部の仕事の話がおもしろい。毎年、10人の職員で1万件の依頼書をさばき、2兆円を世界中に貸し付けている。JICA新人時代にアフリカへの貸付実行モニタリングを担当したのが思い出。先輩職員のところへ行き、「何が原因で予定通りにいかないんですか」と聞いて回る仕事。
スリランカ産業省がやる気を見せなかったので、支援計画を止めて、自発的に解決策を模索する地方政府と案件形成をした話はおもしろい。日本がやりたいことを押し付けているんじゃないか、と言う人もいますが、要請主義の現場がよく書かれているので読んでみるとよいです。
ウズベキスタンの汚職撲滅プロジェクトやジェンダー案件の話など。職員個人も組織としても経験値の低い分野であっても、国の要請に応じる形で事業形成していく話は、多くの読者の想像を超える仕事なのではないかと思います。
「日本から開発途上国に流入する資金のうちODAが占める割合は一~二割・・これからは民間」というくだりからは、卒業国は民間へ託し、ODAは引き続き先兵として西へ針路をとっていくという今後の流れが想像できます。
【非表示のコンテンツがあります。この内容を閲覧するにはログインが必要です。】