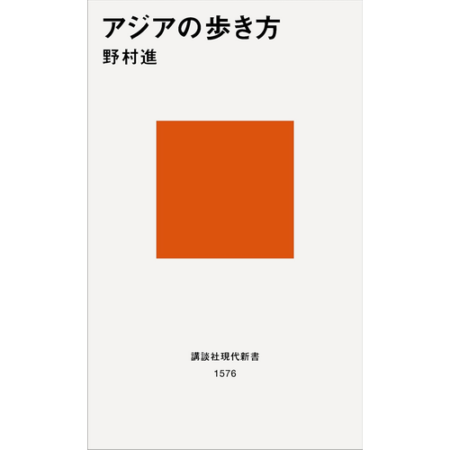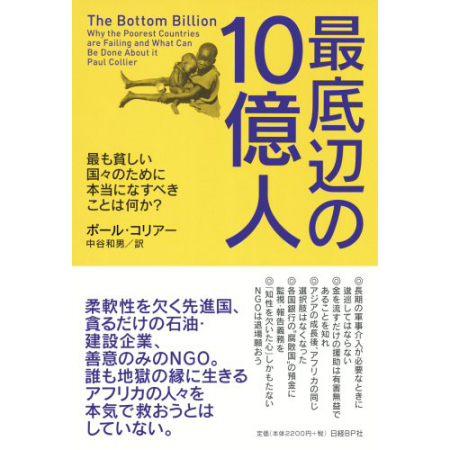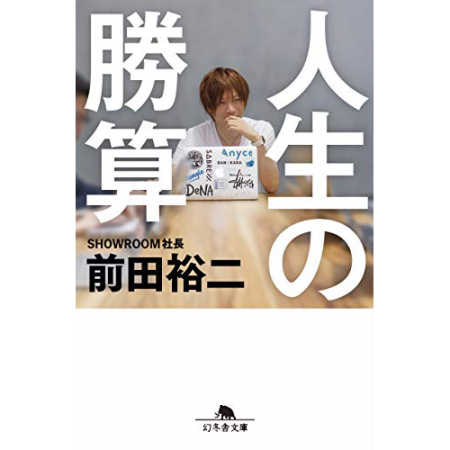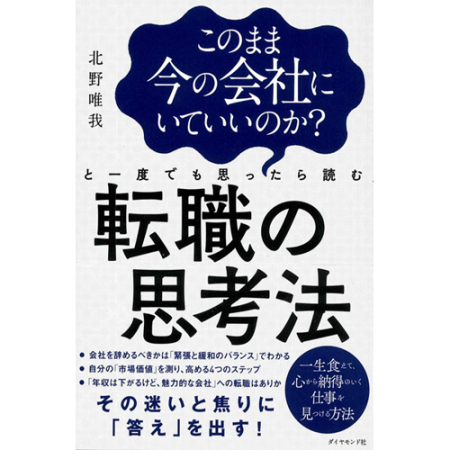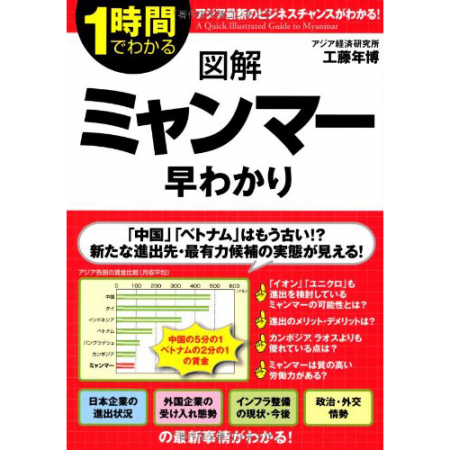アジアの歩き方
¥770
「私が下宿していた地域は、日本人の目にはスラムと映るだろうが、マニラでは中下層の庶民が住むところだった。」
この本の好きな所は、こうした著者のスタンスが庶民目線なところ。東南アジアに駐在する知人の多くが庶民とは離れた生活をしているが、私は著者の間隔に近い。
日本に招いたインド人が持参した小麦でチャパティを作り、持参したスパイスでカレーを作り、一切和食を受け付けなかったというエピソードもおもしろい。筆者はインド文化の強靭な固有性と呼んでいるが、留学・仕事を通じて接したインド人は、融通の利かなさと頑固さを兼ね備えた人も多かった。
その続きもある。日本を訪れたインド人が唯一おいしいと言ったのは、ファミレスのナポリタンにタバスコをかけたものと、紅茶に砂糖とミルクを大量に入れたものだった。食後にはテーブルにあった砂糖袋とミルク容器の山ができていた。
インドネシアの国民感情についても、現地で商売をしている日本人の話を引用している部分が示唆に富んでいる。ジャワ人が日本人を見て外人と認識するのと、バジョ人に抱く外人意識はほぼ同じ。インドネシアには国境と国籍こそ一つだが、民族間にある外人意識と緊張感は大きい。これは行政・政治・政策対話を見ていて、肌で感じる。
中国で商売をするときに大切なのは、中国が法治国家ではなく人治国家だと理解することだとする評価もおもしろい。法よりも権力を持つものこそが優先されるのだ。人治主義とそれに伴う汚職を東南アジアに広めたのは、中国大陸からの華僑だと、台湾の李登輝総統が言っていたのを思い出した。
また、中国人は一人一人が意見を持っているのではなく、権力者の意見になびいて、結束を固め、暗黙の了解で寝返るやつがいないとする、現地で商売をする日本人のコメントも興味深い。私の感覚からすれば、この評価はインドネシア人にも極めて近い感覚を覚えることが多い。労組・デモ・政治・対話など、ほとんどの人は意見を持っていないがついていく。
【非表示のコンテンツがあります。この内容を閲覧するにはログインが必要です。】